2021年10月に開催された金沢マラソン。4時間30分のペースランナーとして参加しました。
自分自身、3回目のペースランナーです。過去に5時間、4時間のペースランナーを同大会で経験しています。
今回は4時間30分のペースランナーの経験を忘備録として残します。
練習内容
ペースランナーといえども、練習はします。
でも、別のレースも控えているのでペースランナーの練習ばかりするわけにはいきません。

月2~3回の設定ペースでの20~25km走
ぼくは普段のジョギングは、4:15 ~ 4:45 /km でやっています。一方、4時間30分のペースランナーの設定ペースは6:15 ~ 6:30 / km です。いつもの練習ペースよりだいぶペースを落とす必要があります。
4時間30分のペースになれるために、月に2~3回 、設定ペースで20~25km 走をしました。
体力的には余裕なのですが、10km 過ぎてからふくらはぎが痛くなることが多かったです。いつもと違う筋肉を使っているからと思います。
レース2週間前の30km走
レース2週間前は、5:00/km ペースで30km走をしました。大会前に30km を走りたかったので実施しました。
サブ3を狙う本番のレースでも2週間には30km走をしています。
この練習は、ペースを気にせず、30km 走り切ることを優先しました。
レース1週間前はジョギングも設定ペースに
レース1週間前からジョギングも設定ペースで行うようにしました。体に設定ペースを刻み込みます。
レース開始時はペースがつかみにくく、ペースが速くなりがちなので、その対策として行いました。
1kmごとのペース配分表
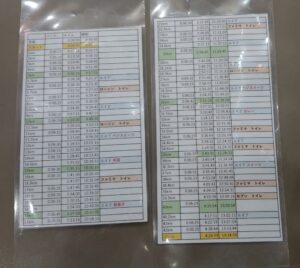
1kmごとのペース配分表を事前に作りました。レース中は両腕に巻き付けて走ります。
1km間隔の到達時間のほか、設定ペース、エイド、トイレの位置も書いてあります。
メリット
一番のメリットは、不安がなくなることです。ペースランナーをしていると、今走っているペースが速いのか遅いのか分からなることがあります。設定ペースよりも遅いのはだめだし、かといって速すぎてもだめです。
なので、不安を解消するため1kmごとのペース配分表を作りました。1km間隔でペースを確認して設定より速いのか遅いのか、それが分かれば次の1kmのペースも決めることができます。
実際、ペース配分表のおかげで、
- 10km 6秒遅れ
- 20km 13秒遅れ
- 30km 2秒速い
- 40km 3秒速い
- ラスト1km 5秒速い
- ゴール ±0( 4時間29分59秒 )
という結果で走れました。
デメリット
この方法のデメリットは細かいペース変化が多くなることです。1kmごとにペースを調整するので、そこでペース変化が発生します。ペース変化はランナーの足に知らず知らずのうちにダメージを与えます。
多少速くても、ペース変化をせずそのまま走り続けたほうがいいかもしれません。
ここは難しいところです。10秒以上遅れていたとしても2~3km使って設定ペースに追いつくという感覚で走るのがよいでしょう。
レース中にかんじたこと

エイドの休憩30秒は無理
給食スポットのエイドは30秒止まる計算をしていました。しかし、休憩時間は30秒より長くなったようでした。30秒くらいのロスのつもりが、おそらく40~50秒になっていたと思います。
給食エイドで止まるならば、50秒くらい休憩時間を見積もってもよいと思います。
ペースランナーといえども走り込みは必要
自分の全力より遅いペースで走るといっても、フルマラソンを走ることには変わりありません。先ほど書いたように、いつもと違う筋肉を使って42.195km 走ります。練習不足の状態で臨むと、急に走れなくなるかもしれません。
調子にのってはいけない
これは、前回のぼくの反省になります。ペースランナーは、沿道の声援にあまり応えないほうがよいです。沿道の声援に応えようとふらふらしていると、ペースが乱れます。
あくまで主役は参加者。参加者が楽しんでもらうよう、ペースランナーは控えめにすべきでしょう。
まとめ
4時間30分のペースランナーの忘備録を書きました。
今後ペースランナーをやる人の参考になればと思います。






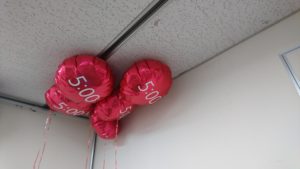

コメント